スタッフブログ
2020/07/10更新
障害年金の請求の流れ
皆様こんにちは
障害年金相談窓口ソシオノームの寺本と申します
このブログでは、皆様に障害年金についてにお伝えしております
これまでに障害年金の手続きに必要な書類について、ブログで紹介してきました
では実際に障害年金の請求を行う場合、請求までどのような流れで進んでいくのでしょうか?
障害年金の請求を行う時には最寄りの年金事務所に行って、年金事務所の方と一緒に請求の手続きを進めて行きます
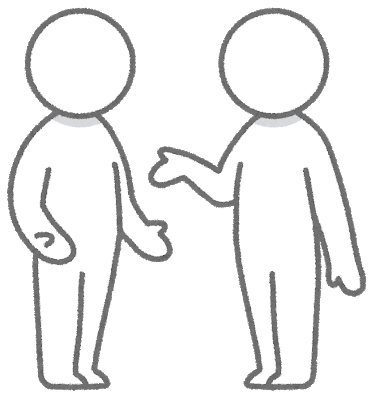 受診状況等証明書の作成
受診状況等証明書の作成
障害年金の請求を行いたい場合は、まず年金事務所に行って相談をします。
障害年金の制度や請求の流れについて教えてもらい、まず最初に行うことは初診日について確定させることです。
障害年金において初診日は、納付要件を確認したり、受け取れる障害年金は国民年金か厚生年金か共済年金か、請求制度はどうなるのかを確認するために必要になります
受給が出来るかどうか、支給額はどのくらいか、また障害状態であることを認定する障害認定日がいつになるのかを決める重要なものになりますので、初診日の証明書が必ず必要になります
年金事務所に行くと、まずは初診日を証明するための
『受診状況等証明書』
を渡されます
この書類を現在の障害の原因となった傷病について、初めて診察を受けた病院に持っていって記入してもらう必要があります
受診状況等証明書の作成には時間がかかることがありますので、作成が終わるとまた病院に受け取りに行きます
受診状況等証明書の作成には料金が掛かります
地域や医療機関によって受診状況等証明書の料金は異なるため、事前に病院に確認しましょう
受診状況等証明書を受け取ると、年金事務所に持って行って年金事務所の方と一緒にチェックをしていただきます
初診日の確認が終わると、保険料を一定期間収めているか確認が行われます
また初診日から1年6か月後の障害認定日が決まります
初診日から1年6か月経った時が20歳よりも前にあったら障害認定日は20歳の誕生日の前日が障害認定日になります
初診日がわかることで、障害認定日が決まり、納付要件を満たしているか確認できますので、今後の請求の流れが決まります
病歴就労状況等申立書の作成
次に『病歴就労状況等申立書』の作成を行います
病歴就労状況等申立書は自分で記入する通院状況や、病状を補足する資料で、こちらは自分で記入する必要があります
障害年金は書類での審査になりますので、発病から現在までの流れがわかるように、詳細に書いていく必要があります
医療機関を受診した期間、受診していない期間なども思い出しながら当時の病状や経過について一連の流れがわかるように鉛筆で下書きをしてまとめます
書き終えたらもう一度年金事務所に行って、きちんとチェックしてもらうようにしましょう
 診断書の作成
診断書の作成
病気の経過や通院歴がわかると、現在の状態を示す診断書を通院先のお医者様に書いていただく必要があります
診断書をもって病院に行き、診断書の依頼をしましょう
診断書は細かな数値や、検査項目などがありますので、作成に時間がかかります
作成が終わると病院へ取りに行きます
診断書の作成には費用がかかります
地域や医療機関によって費用が異なりますので、作成を依頼する際には証明書の代金について確認しておきましょう
診断書を年金事務所に持って行って、きちんと不備がないかもチェックをしてもらうようにします
自身で記入した病歴就労状況等証明書などと整合性が取れているかどうかも併せて確認し、必要があれば病歴就労状況等証明書も訂正しましょう。
添付書類を揃える
初診日を証明する受診状況等証明書
現在の症状を表す診断書
ご自身でまとめる現在の症状や生活状況等を伝える病歴就労状況等証明書
これらが揃ったら、そのほかに必要な添付書類を集めます。
・年金手帳の写し 年金番号を確認するため
・住民票 本人の生年月日や住所を確認するため
・銀行口座の写し 年金の振込先を確認するため
18歳年度末までのお子様、または20歳未満で障害のあるお子様がいる場合には2級以上で加算で年金がもらえますので、以下の書類も別途必要になります
・戸籍謄本 お子様との続柄と、お子様の名前と生年月日の確認の為
・世帯全員の住民票 家族の生計維持関係を確認するため
・お子様の所得証明書 お子様の加算条件として年収が850万円以下であるかどうかを確認するため
・学生証 高等学校などに通われている場合は学生証のコピー
・お子様の診断書 20歳未満で障害のあるお子様がいる場合、障害状態が1級または2級であることを確認するため
障害厚生年金の場合は2級以上で配偶者の方への加算も付きますので、以下の書類が必要になります
・配偶者の方の所得証明書
障害の原因が交通事故など第三者行為による場合はまた別途こちらの書類が必要になります
・第三者行為事故状況届 所定の様式があります
・確認書 所定の様式があります
・交通事故証明 事故があった際に届く事故の証明書、または事故があったことを記す新聞の記事の切り抜きなど
・被害者に扶養者がいる場合は、源泉徴収票、健康保険所のコピー、学生証のコピーなどを一緒に添付します
・損害賠償額の算定書 損害賠償額がすでに決定している場合に必要、損害賠償金をいくら受領したかが記された示談書など
請求者の状況に合わせて必要な物
・呼吸器疾患の場合、診断書と一緒に胸部X線写真(レントゲン)も一緒に添付する必要があります
・循環器疾患の場合、心電図の所見がある方は、診断書と一緒に心電図のコピーも一緒に添付する必要があります
・障害者手帳の写し 障害者手帳がある場合、障害状態を補足する資料として、手帳の写しを一緒に添付します
・年金証書 ほかに公的年金を受給している場合に提出します
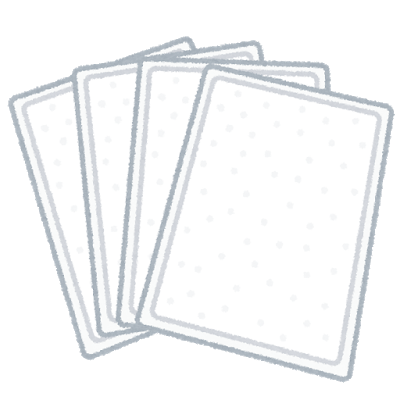 年金請求に行く
年金請求に行く
必要書類をもって年金事務所に行くと、最後に年金の裁定請求書を記入します
これまでに集めた書類を見ながら間違えないように記入します
印鑑を押す箇所がたくさんありますので、認印を持っていきましょう
このように障害年金の請求は必要書類の多さから、多くの工程を要します
中には作成までに時間がかかるものや、もらったはずなのに紛失してしまって再発行が必要な物など、時間も労力も必要とします
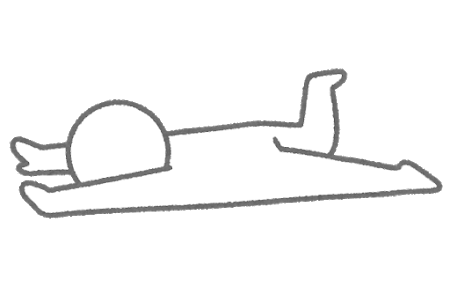
障害年金相談窓口ソシオノームでは、障害年金に関する難しい請求業務を一緒にお手伝いをしながら進めて行くことが出来るスタッフが揃っております
取得するのに大変な書類や、病歴についてまとめていく病歴就労状況等証明書の作成、年金事務所へも代わりにお伺いして請求を安心して進めて行けるようにお手伝いをしていますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください

 障害年金相談窓口ソシオノーム
障害年金相談窓口ソシオノーム
寺本
